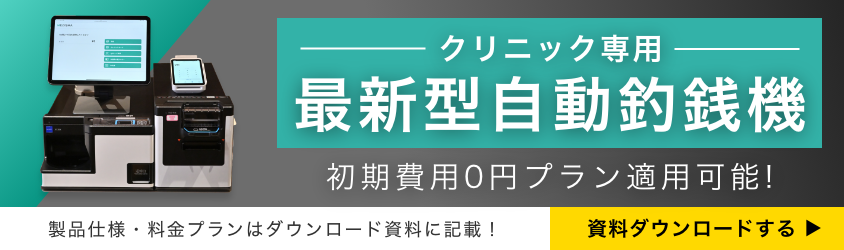開業医のための電子決済手数料対策|医療機関キャッシュレス化に向けて
- 2025年6月24日
- 自動精算機

コロナ禍を境に、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済などの「キャッシュレス決済(電子決済)」が医療機関でも利用されるようになってきました。特に、若い世代を中心に利用されており、患者さんからのニーズも高まっています。
一方で、キャッシュレス決済を導入するには、システム導入費用だけでなく、電子決済手数料やさまざまなコストが発生します。クリニックは、自院の電子決済手数料の負担がどのくらいか知っておくことが必要です。
この記事では、医療機関のキャッシュレス決済で忘れてはいけない「電子決済手数料」について解説します。また、クリニックで導入する際のメリット・デメリットについて紹介するので、キャッシュレス決済の利用を検討しているクリニックはぜひ参考にしてください。
Table of Contents
【そもそも】電子決済の仕組みと「手数料」の正体
厚生労働省の調査によると、クレジットカード決済を導入している医療機関は2023年時点で「導入している」が62.6%、「導入を検討している」が1.5%、「導入していない」が35.9%となっています。
6割以上の医療機関が利用していることがわかります。
しかし、クレジットカード決済には手数料がかかり、利用者が多くなるほど医療機関の負担も大きくなるため、悩んでいる医療機関が多いのも事実です。
そのため、電子決済を導入する場合は手数料の負担も含めて検討する必要があります。
また、電子決済には以下のような種類があり、それぞれ手数料も異なるため注意してください。
- クレジットカード:3~5%程度
- 交通系ICカード:3~4%
- QRコード決済:0〜3%程度
たとえば、1,000円の医療費に対して3%の手数料がかかる場合、1回の決済で30円の手数料が発生するため、患者数の増加に伴い手数料の負担は大きくなりがちです。
電子決済を導入すると、端末の設置費用や月額利用料が別にかかる場合もあるため事前に確認しておくと安心です。
【保険診療vs自由診療】どちらに向いてる?電子決済導入の見極め
クリニックの診療には保険診療と自由診療の2種類があります。
クリニックで電子決済を利用する際は、保険診療ができるかによって使いやすさが変わってきます。
保険診療
多くのクリニックでは基本的に保険診療をおこなっているため、患者さんの支払う金額は全体の1〜3割です。
保険診療では、患者さんの負担額は1〜3割と少なく、クリニックの場合は比較的、診療単価も低いため、手数料の負担は少ないです。
例えば、3割負担で診療費が3,000円の場合、患者さんの支払いは900円です。そこから3%の手数料なので27円差し引かれる形です。
1人あたりの手数料は少ないですが、患者さんの数が多い回転率の良いクリニックの場合は、キャッシュレス決済が多いほど手数料がかかってしまいます。
自由診療
美容医療や予防接種、人間ドックなどのように、患者さんが全額支払う自由診療を扱うクリニックもあります。
自由診療は全額負担になるため高単価なことが多く、1人あたりの手数料の影響が大きくなります。
診療費が3,000円の場合、患者さんは全額負担するため、3%の手数料だと300円差し引かれる計算です。
また、キャッシュレス決済に対応することで、手持ちのお金がなくても受診できるようになるため、患者さんの受診のハードルが下がります。
自由診療に該当するような美容医療や予防接種などは、若い患者さんを対象とするものが多いです。
支払いの選択肢が増えることで、患者さんも利用しやすくなり、結果的に満足度やリピート率の向上にもつながるでしょう。
【メリット】電子決済導入による利便性・集患・業務効率化

電子決済を導入すると、会計の手間を減らすだけでなく、クリニックの運営にも以下のような3つのメリットがあります。
- 「現金を持たない世代」の集患
- スタッフの会計業務のミス軽減と時短
- POS・レジとの連携による売上管理の簡素化
それぞれ解説していきます。
「現金を持たない世代」の集患
キャッシュレス対応のクリニックは現金を持ち歩かない世代の患者さんに選ばれやすくなります。
20代〜40代の若い世代の患者さんは、スマートフォンで決済するのが当たり前のようになってきました。
そのため、電子マネーやQRコード決済などに対応していると、それだけで来院のハードルが下がり、集患につながりやすくなります。
ほかにも自費診療では、電子決済の利用が患者さんの支払いのハードルを下げるポイントになります。
高額になりがちな自費診療でも、クレジットカードや分割払いに対応していれば、単価の高い診療でもスムーズな提供が可能です。
スタッフの会計業務のミス軽減と時短
キャッシュレス決済により受付での現金の取り扱いが減ることで、スタッフの負担も軽減されます。
おつりの間違いや入金ミスなどが減り、ヒューマンエラーの防止に役立つのがポイントです。
現金の取り扱いが減り、ヒューマンエラーの防止につながることで、スタッフの精神的なストレスも減少するでしょう。
医療系POSレジとの連携による売上管理の簡素化
医療系POSレジや会計ソフトをうまく連携させることで、毎日の売上や患者ごとの支払い情報を自動でまとめることができます。手作業での入力や集計がほとんど不要になり、スタッフの事務作業の時間の短縮が可能です。
月末や年度末のレポート作成もスムーズになり、経理の負担が減るだけでなく、クリニック全体の運営が効率よく進められます。時間に余裕が生まれることで、患者さん対応や他の重要な業務にもより集中できるようになるでしょう。
【デメリットと対策】手数料の負担、どう考える?
電子決済の導入によるデメリットは以下の2つがあります。
- 手数料3%による利益圧迫
- 入金の遅れ
それぞれ解説していきます。
手数料による利益圧迫
電子決済導入の一番のデメリットは「手数料」です。
利用すると平均して3%前後の手数料が発生するため、患者数が増えるほど、クリニックのコストが大きくなります。
ただし、こういったデメリットも以下のような工夫次第でクリニックの支払いは抑えられます。
- 手数料が低いQRコード決済や電子マネーを優先的に導入する
- 自費診療はクリニックで価格を設定できるため、価格に手数料を含めて設定する
あらかじめ、手数料がかかるかを考えておくことで、クリニックの経営を圧迫せずに運営できるでしょう。
入金の遅れ
電子決済の注意点として、すぐに入金されないため気をつけなければなりません。
電子決済の場合、現金と異なり、患者さんではなく決済会社から入金されるため、クリニックに実際にお金が入るのが遅くなります。
入金のタイミングは決済方法や会社によって異なります。
クリニックの経営にかかわってくるので、電子決済の種類ごとにいつ入金されるかをチェックしておきましょう。
【おすすめの運用体制】電子決済は“選べるようにする”のが基本
クリニックで電子決済を導入する場合、すべての支払いを電子決済にする必要はありません。
現金、電子マネー、クレジットカード、QRコード決済を併用し、患者さんが支払い方法を選べるようにするのが理想的です。
例えば、高齢者の多い診療科で電子決済のみは現実的ではありません。
また、若い世代でも現金派の人もいるため、電子決済だけにしてしまうと一定の患者さんは利用しなくなってしまいます。
そのため、患者さんの年代や診療内容に応じて使い分ける方法が効果的です。
自由診療をおこなっている場合は、まずは自由診療だけ電子決済を利用し、使い勝手を確認しながら保険診療にも広げていくような、部分導入から始めるのもおすすめです。
【メディスマレジの活用】医療現場に特化したレジシステムの強み
「メディスマレジ」は、医療機関向けに設計されたレジシステムです。保険診療と自由診療のどちらにも対応しており、会計業務を効率よく進められます。
電子決済システムは、従来のレジに後付けできるものもありますが、メディスマレジを導入することで、院内のシステムと連携でき、一元管理もできるため業務の効率化を実現可能です。
電子カルテや予約システムと連携すれば、受付から会計までの流れをスムーズに自動化できます。
クレジットカードや電子マネー、QR決済などさまざまな決済手段にも対応しているため、患者さんの希望に合わせられるでしょう。
手数料を可視化したり、売上レポートの出力機能も備えたりしているため、経営面でのコスト管理にも役立ちます。
また、インボイス制度や電子帳簿保存法への対応も見据えた設計になっており、将来的な制度変更にも対応できるため安心して使用できます。
まとめ:クリニックの選択肢
電子決済は手数料がかかる一方で、患者さんの支払いの選択肢が増えるだけでなく、スタッフにとって業務の効率化が可能です。
全体としての経営的なメリットを考えると、導入を前向きに検討する価値があります。
電子決済を導入する際には、クリニックの診療スタイルや患者層に合った決済方法を選びましょう。
すべてを一度に変える必要はなく、まずは自由診療から始めるなど、無理のない範囲で取り入れていくのが現実的です。
導入時は、レジや会計業務全体を見渡して、医療系POSレジのメディスマレジのように一元管理できる仕組みを活用すると、よりスムーズな運用ができるようになります。
興味があれば、無料デモ体験やコンサルティングを利用して、自院に合った運用方法を見つけてみてください。
<参考サイト・文献>
「令和5年度 医療機関における外国人患者の受入に係る実態調査」|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001292094.pdf
著者PROFILE

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、クリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。