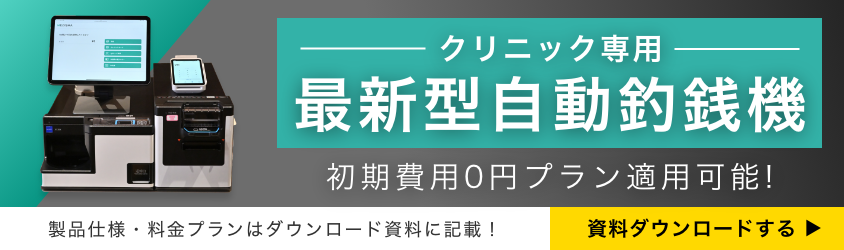歯科クリニックに自動精算機を導入するメリットとは?業務効率と患者満足度を両立する最新ソリューション
- 2025年8月20日
- 自動精算機

「歯科医院の会計業務をもっと効率化したい」「患者さんの待ち時間を減らしたい」
このようにお考えではありませんか。
自動精算機は、会計業務を自動化するシステムで、近年多くの歯科医院で注目を集めています。
自動精算機を導入すれば、スタッフの業務負担を減らし、患者さんの満足度を高められます。
しかし、費用や種類、選び方など、導入にあたってさまざまな疑問を持つ方も多いでしょう。
この記事では、歯科クリニックに自動精算機を導入するメリットや選び方を、わかりやすく解説します。
Table of Contents
歯科クリニックで自動精算機の導入が進む背景
受付業務の負担や、患者さんの会計待ち時間に課題を感じている歯科クリニックが増えています。
そんな中で、医療DX推進、感染症対策、人手不足への対応といった背景から、自動精算機の導入が進んでいます。
医療DX推進と受付業務の省人化ニーズ
多くの歯科クリニックで自動精算機の導入が進むのは、厚生労働省の取り組みの1つに医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が挙げられているからです。
受付の仕事をデジタル化して、スタッフの人数を減らしたり、負担を軽くしたりしたいというニーズがあります。
デジタル技術を使って受付の仕事を自動化すれば、スタッフの負担を減らせるでしょう。
例えば、自動精算機を導入すると、受付スタッフがお金のやりとりをする必要がなくなります。
スタッフは患者さんの対応や診療補助など専門的な業務に集中できるようになる結果、クリニックのサービスが良くなり、人件費の削減やスタッフの離職率低下も期待できます。
コロナ禍による非接触ニーズの拡大
コロナ禍をきっかけに、患者さんが安心して来院できる環境づくりが重要になりました。
特に、非接触で会計を済ませたいというニーズが増加しました。
自動精算機を導入すれば、スタッフとの金銭の受け渡しがなくなるため、感染リスクを減らせます。
多くの自動精算機は、クレジットカードや電子マネーといったキャッシュレス決済に対応しており、現金の受け渡しをせずに支払いを済ませられるため、安心して会計ができます。
人手不足とスタッフの業務負担軽減への対応
人手不足が深刻な歯科業界では、スタッフの業務負担を減らす対策が急務です。
自動精算機は、受付業務の効率化によりスタッフの負担を大幅に軽減できます。
会計業務は、診療費の計算やお金の受け渡し、レジ締め作業など、多くの時間と手間がかかります。
例えば、自動精算機を導入すると、レジ締め作業は数分で完了するため、残業時間が減るでしょう。
スタッフの負担が減ると、労働環境が改善されるため、定着率の向上にもつながります。
歯科クリニックにおける自動精算機の主なメリット

自動精算機を導入すると、受付スタッフの業務効率が上がり、患者さんの満足度も向上します。
会計業務の自動化によりヒューマンエラーを防ぎ、スムーズな会計が実現できます。
会計業務の効率化と人件費削減
自動精算機を導入すれば、会計業務の大部分を自動化できるため、効率化と人件費の削減が実現できます。
診療費の計算やお金の受け渡し、釣り銭の管理、レジ締めといった作業は、自動精算機がすべておこないます。
例えば、次のような人手が必要な業務に集中できるようになるでしょう。
- 予約管理
- 電話対応
- 患者さんの問診
受付スタッフの人数を減らせるため、人件費の削減にもつながります。
患者の待ち時間短縮と満足度向上
自動精算機は、患者さんの待ち時間を短縮し、満足度を向上させます。
その理由の1つが、混雑する時間帯でもスムーズな会計ができるからです。
クリニックが混雑していると、会計の待ち時間が長くなり、患者さんにストレスを与えてしまいます。
自動精算機があれば、患者さんが自分で会計を済ませられるため、受付の混雑を緩和できます。
また、クレジットカードや電子マネーなどの多彩な決済方法に対応しているため、患者さんは自分の都合に合わせた支払いが可能です。
感染症対策としての非接触会計
自動精算機は、感染症対策としても有効な手段です。
スタッフと患者さんの間で金銭のやりとりがなくなるためです。
自動精算機は、現金やキャッシュレス決済など、患者さんが自分で支払いをおこなえるシステムです。
スタッフが現金を触る必要がなくなるため、感染リスクを減らせます。
スタッフも患者さんも安心して会計できるため、クリニック全体の感染症対策の強化につながります。
レセコンや電子カルテとの連携で業務全体の最適化
自動精算機は、レセプトコンピューター(レセコン)や電子カルテと連携できる機種が多く、クリニック全体の業務を最適化できます。
レセコンや電子カルテから診療費データが自動で送られ、会計情報が自動で共有されるため、会計金額の入力ミスを防げます。
これにより、ヒューマンエラーが減り、会計業務の正確性が向上するはずです。
会計記録も自動で残るため、日々の業務管理が楽になるでしょう。
自動精算機を導入するメリットは、下記の記事でも詳しく解説しています。
小型の自動精算機をクリニックに導入するメリット5選!卓上タイプの価格
導入前にチェックすべきポイント
歯科クリニックに自動精算機を導入する際は、機種選びが重要です。
クリニックの規模や患者数、既存システムとの連携、サポート体制などを考慮して、最適な機種を選ぶ必要があります。
歯科クリニックの規模と患者数に応じた機種選定
歯科クリニックに自動精算機を導入する際は、規模と患者数に合った機種を選びましょう。
一例として、患者数が多い大規模なクリニックでは、処理速度が速く、多彩な決済方法に対応している機種が適しています。
一方、小規模なクリニックでは、省スペースな卓上型や、初期費用を抑えられる機種がおすすめです。
クリニックの環境やニーズに合わせて最適な自動精算機を選べば、導入効果を最大限に高められます。
レセコン・電子カルテとの連携可否
歯科クリニックに自動精算機を導入する前に、既存のレセコンや電子カルテと連携できるかを確認してください。
連携機能があれば、会計情報が自動で取り込まれるため、手動で金額を入力する必要がなくなります。
これにより、入力ミスや手間を減らせます。
導入を検討する際は、現在使っているシステムと連携できるかを確認しましょう。
サポート体制・保守対応の有無
自動精算機を安心して使い続けるためには、メーカーのサポート体制が重要です。
自動精算機は精密機器であるため、故障や不具合が起きる可能性があります。
サポート体制が充実しているメーカーを選べば、トラブルが起きてもすぐに解決できます。
導入後の保守対応やサポート窓口の有無を確認しておきましょう。
キャッシュレス・各種決済対応の柔軟性
患者さんの利便性を高めるために、さまざまな決済方法に対応している自動精算機を選びましょう。
患者さんのニーズに幅広く応えられるからです。
現金払いの他に、クレジットカードや電子マネー、QRコード決済など、多様な決済方法に対応している機種が増えています。
多くの決済方法に対応していれば、患者さんは好きな方法で支払いができます。
自動精算機を導入する前に押さえたいチェックポイントについて、下記の記事でも詳しく解説しているため、参考にしてみてください。
クリニックの会計をスムーズに!失敗しない自動精算機導入のチェックポイント
メディスマレジの自動精算機が選ばれる理由
メディスマレジの自動精算機は、歯科業界に特化した設計と機能が大きな特徴です。
手厚いサポート体制と多彩な決済方法に対応しているため、多くの歯科クリニックに選ばれています。
歯科業界に特化した設計と機能
メディスマレジは、歯科業界に特化した設計と機能で多くのクリニックに選ばれています。
一般的なレジとは違い、歯科医院の診療費や物販品の両方に対応できます。
バーコードを読み取ることで会計金額が自動で入力されるため、打ち間違いを防げるのです。
現金の受け渡し作業がなくなり、スタッフの負担を大きく減らせるなど、歯科に特化した機能が、日々の業務をスムーズにできるでしょう。
導入から運用までの手厚いサポート体制
メディスマレジは、導入から運用まで手厚いサポート体制を整えています。
初めて自動精算機を導入する歯科クリニックでも、安心して使えるでしょう。
導入時には専門スタッフが設置や設定をおこない、操作方法を丁寧に説明します。
また、導入後も電話やメールでのサポート、さらには現地訪問でのサポートも提供しています。
万が一のトラブル時も、すぐに相談できる体制があるので、スムーズな運用を続けられるのです。
多彩な決済対応と柔軟なカスタマイズ性
メディスマレジは、多彩な決済方法に対応し、クリニックに合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。
現金はもちろん、クレジットカード、電子マネー、QRコード決済にも対応しています。
患者さんは自分にとって便利な支払い方法を選べるため、満足度が向上します。
さらに、クリニックの診療スタイルやスペースに合わせて、最適な機種や機能を選べるのも大きな魅力です。
まとめ

歯科クリニックにおける自動精算機の導入は、業務効率化と患者さんの満足度向上を両立させる有効な手段です。
受付業務の負担を減らし、患者さんの待ち時間を短くすることで、歯科クリニック全体のサービス向上につながります。
導入を検討している方は、歯科クリニック専用機のノウハウと実績を持つメディスマレジへぜひご相談ください。
<参考サイト・文献>
医療DXの更なる推進について|厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/10801000/001274832.pdf
著者PROFILE

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、クリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。