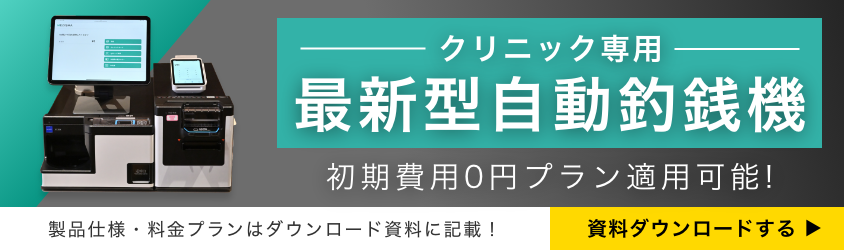自動会計機がクリニックの受付を変える!業務効率化や感染対策も対応
- 2025年4月10日
- 自動釣銭機・セミセルフレジ

新型コロナウイルスの流行以降、クリニックは感染対策のためにアルコール消毒をしたり、患者さんの検温をしたりと大きく変化しました。
そこで注目されているのが、受付業務を一新する「自動会計機」の導入です。クリニックの感染対策の強化をはじめ、患者さんがより安心して通える環境づくりに大きく貢献するものと期待されます。
自動会計機には、非接触・省人化・業務効率化という三拍子の特徴が揃っているため、受付の混雑を解消し、スタッフの業務負担を軽減することができます。
これにより、クリニックの限られたスタッフでも効率的でスムーズな運営が可能になります。
この記事では、自動会計機が必要な背景や導入によるメリット、実際の導入事例まで、くわしくお伝えします。
会計業務の効率化を実現したいクリニックは、ぜひご覧ください。
Table of Contents
なぜ今「自動会計機」なのか?
近年、私たちの感染に対する意識は大きく変わり、医療現場では感染対策が徹底されるようになりました。
そこで注目を集めているのが「自動会計機」です。
注目されている理由として、具体的には以下の3つが挙げられます。
- 非接触の受付ができる
- 受付を省人化できる
- 業務を効率化できる
多くのクリニックでは、人手が足りずに困っていることがよくあります。そのような状況では、少ないスタッフで受付業務をこなさなければなりません。
厚生労働省の調査によると、患者さんは待ち時間が長くなると不満を感じやすくなるという報告があります。
こうした問題を解決するために、自動会計機はクリニックの運営をスムーズにするうえで、とても役立つツールです。
手作業による受付・会計で起きやすい3つの問題
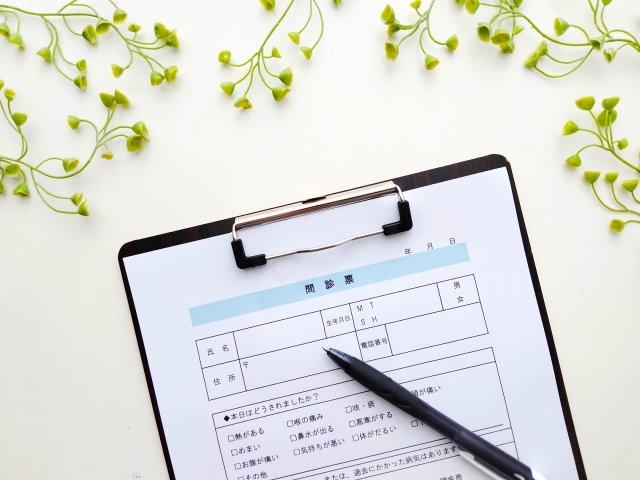
受付や会計を手作業でおこなっているクリニックでは、次のような問題がよく見られます。
・待ち時間が長くなる
・感染リスクが高くなる
・事務スタッフの負担が大きくなる
それぞれの問題について、詳しく説明します。
1. 待ち時間が長くなる
手作業で受付や会計を行っていると、どうしても処理に時間がかかります。
そのため、ロビーが混雑しやすくなり、患者さんの待ち時間が長くなってしまいます。
これにより、患者さんの満足度が下がる原因になります。
2. 感染リスクが高くなる
受付に人が集中して混雑すると、密な状態になりやすくなります。
とくに感染症が流行している時期には、こうした密集が感染リスクを高めてしまうため、注意が必要です。
3. 事務スタッフの負担が増える
受付や会計を手作業で行うと、スタッフの業務量が多くなります。
たとえば、診療報酬の計算や会計処理、月末の締め作業など、手間のかかる業務がたくさんあります。
その結果、ミスが起きやすくなり、残業が増える原因にもなります。
自動会計機がもたらす5つのメリット
長い待ち時間やスタッフの業務負担を解消するためにおすすめなのが、自動会計機の導入です。
導入により以下の5つのメリットが期待できます。
- 会計のスピードアップと待ち時間の削減
- 非接触対応で感染対策が可能
- スタッフの業務負担を軽減し、医療サービスに集中できる
- 金銭トラブル・ミスの削減
- 経営データの可視化
それぞれ具体的に解説していきます。
導入を検討しているクリニックはぜひ参考にしてください。
1. 会計のスピードアップと待ち時間の削減
自動会計機を導入するメリットのひとつが、会計処理のスピードが早くなる点です。
従来の手作業による会計では、診療報酬の算定から金額の入力、領収書の発行までに多くの作業が必要で、患者さんが診察を終えたあとも長時間待たされることが多々ありました。
しかし、自動会計機を導入することで、診療内容に応じた金額が反映されるようになります。
患者さんは診察後、スムーズに精算を済ませるため、待ち時間が短縮されます。
2. 非接触対応で感染対策が可能
自動会計機の大きな特長のひとつが「非接触対応」で感染対策が可能な点です。
これまでの受付や会計業務では、スタッフと患者さんの間で現金や領収書、明細書の手渡しで接触がありました。
インフルエンザや新型コロナウイルスのような感染症が流行する季節には、接触により感染のリスクが高まりがちです。
しかし、自動会計機の導入により、接触を最小限に抑えられます。
診療が終わると、患者さんが機械を操作して会計をおこないます。
また、現金や紙の書類は人の手を介さずにやりとりが可能です。
さらに、キャッシュレス決済にも対応しており、あらゆる年齢層の患者さんにとって利用しやすくなっています。
3. スタッフの業務負担を軽減し、医療サービスに集中できる
クリニックの事務では、限られた人数で次のような業務をおこなう必要があります。
- 診療報酬の算定
- 会計金額の計算
- 領収書の発行
- 会計の締め処理など
これらの作業を手作業でおこなう場合、業務の負荷がかかります。
しかし、自動会計機を導入して会計業務が自動化されれば、スタッフに余裕ができます。
これにより、患者対応や医師の補助といった他の業務に集中できるようになります。
また、業務負担が軽減されることで、スタッフのモチベーションを維持でき、離職率の低下にもつながるでしょう。
4. 金銭トラブル・ミスの削減
診療報酬の計算や金額の入力は、間違いが許されない大切な作業です。
そのため、スタッフには常に高い集中力と正確さが求められ、精神的な負担も大きくなります。
しかし、人の手で行っていると、どうしても*お釣りの渡し間違いや金額の入力ミスなどの「ヒューマンエラー」を完全になくすのは難しいのが現実です。
このようなミスが起きてしまうと、
- 患者さんからの信頼が揺らぐ
- ミスの修正や確認に時間がかかり、スタッフの負担が増える
- スタッフがストレスを感じ、仕事への意欲や効率が下がる
といった問題が発生します。
そこで役立つのが、自動会計機の導入です。
自動会計機は、診療データと連携して金額を自動で計算・入力してくれるため、入力ミスや計算間違いのリスクを減らすことができます。
また、現金の受け渡しも機械が正確に行うので、
- お釣りの渡し間違い
- 金額確認の漏れ
などのトラブルも大きく減ります。
その結果、スタッフは安心して仕事に集中でき、患者さんにも丁寧に対応できるようになります。
5. 経営データの可視化(レセコン連携・POS管理)
自動会計機は、レセプトコンピューター(診療報酬を計算・管理するシステム)やPOSシステム(売上情報をリアルタイムで管理するシステム)とつなげることで、クリニックの経営に関するデータをひとつにまとめて管理できるようになります。
これまで、診療報酬の計算・売上管理・会計処理などを別々のシステムや手作業でおこなっていた場合は、
・情報の集計や分析に時間がかかる
・入力ミスが起きやすい
・データがバラバラになり、管理が大変
といった問題がありました。
しかし、自動会計機を導入すれば、
・診療内容に合わせた会計金額が自動的にレセコンに入力される
・POSシステムを通じて、そのまま売上データとして反映される
ため、正確でタイムリーな経営状況の把握ができるようになります。
これにより、日々の収支確認はもちろん、「どの診療が収益につながっているか」や「患者数や売上の傾向」など、さまざまな角度からのデータ分析が簡単にできるようになり、クリニックの経営判断もしやすくなるでしょう。
実際の導入事例:内科クリニックでの変化
ある一般内科のクリニックでは、自動会計機の導入によって業務効率が大きく改善されました。
導入前は、スタッフが手作業で会計処理をしており、患者さん1人あたりの会計に時間がかかっていました。
そのため、夕方の混雑時にはロビーに10人以上が並ぶこともあり、待ち時間が20〜30分になるケースも。これが患者さんの不満の原因になっていました。
しかし、自動会計機の導入後は、会計待ちの時間が平均5〜10分ほどに短縮され、ロビーの混雑も解消。診察後すぐに会計を済ませて帰れる患者さんが増えたため、「待たずに帰れて助かる」といった声が多く聞かれるようになりました。
また、事務スタッフにとっても大きなメリットがあります。
これまで会計の締め作業に毎日30分以上かかっていたのが、わずか5分程度で終わるようになり、以前は当たり前だった残業が大幅に減少。
あるスタッフは「毎日定時に帰れる日が増えて、仕事に余裕が持てるようになった」と話しています。
さらに、高齢の患者さんや機械操作が苦手な方のために、導入初期は案内スタッフを配置して丁寧にサポート。自動会計機はボタン操作がわかりやすく、画面表示も大きく見やすいため、トラブルもほとんど起きませんでした。
その結果、患者さんからの不安や混乱も少なく、スムーズな導入と高い満足度を実現することができました。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 高齢の患者さんでも使えますか?
A. はい、使えます。
自動会計機は、大きくて見やすいボタンやわかりやすいイラスト付きの画面、音声ガイドなどがついていて、高齢の方や機械が苦手な方でも安心して操作できるようになっています。
また、使い方を説明する案内掲示を設置したり、スタッフが横について一緒に操作をサポートする体制を整えることで、さらにスムーズにご利用いただけます。
Q2. 導入にはどれくらい費用がかかりますか?
A. 初期費用は約100万〜400万円が目安です。
導入する機種によって費用は異なりますが、一般的な価格帯は100万〜400万円ほどです。
また、地域によっては自治体の補助金が使えることもあり、申請することで費用を抑えられる可能性があります。
ランニングコスト(維持費)については、保守契約やメンテナンスの内容によって調整が可能なので、事前に確認すると安心です。
Q3. レセプトコンピューター(レセコン)とちゃんと連携できますか?
A. はい、スムーズに連携できます。
たとえば「MEDIREGI(メディレジ)」といったクリニック向けの自動会計機は、主要なレセコンと接続できるように設計されています。
導入の際には、販売会社(ベンダー*)が初期設定や連携作業をサポートしてくれるため、専門的なITの知識は必要ありません。安心して導入いただけます。
※ベンダー:自動会計機を販売し、設置やシステム連携をサポートする会社です。
Q4. キャッシュレス決済はできますか?
A. はい、対応しています。
クリニックの方針や契約内容によりますが、クレジットカード、QRコード決済(PayPayなど)、電子マネー(Suicaなど)に対応しています。
これにより、現金を持たない患者さんにも便利で、幅広いニーズに応えることができます。
今こそ“受付改革”を進めるタイミングです

コロナ禍を経て、クリニックには非接触で効率的な運営が強く求められるようになりました。そこで注目されているのが、「自動会計機」の導入です。これにより、以下のようなメリットが得られます。
- 待ち時間の短縮
- 感染対策の強化
- スタッフの業務軽減
- 経営データの“見える化”
また、画面は見やすく、操作もシンプル。音声ガイドや大きなボタン付きで、高齢の患者さんでも安心して使えるよう配慮されています。
今、クリニック運営で求められているのは、「よりよい医療サービスの提供・継続」と
「スタッフの負担を軽くする仕組みづくり」の両立です。
その解決策のひとつが、「MEDIREGI」のような使いやすく、高性能な自動会計機の導入です。簡単な操作と正確な処理で、会計ミスの防止、スタッフの業務軽減、患者満足度の向上をサポートします。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
著者PROFILE

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、クリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。